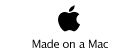研究室のメンバー

ポスドク
特別研究員:
芳賀 和樹
筑波大学大学院博士後期課程修了。博士(農学)。林業史の加藤衛拡先生の愛弟子。共生持続社会学専攻の高橋美貴先生(漁業史、生業史、環境文化史)のもとで日本学術振興会特別研究員PDをこの4月から。縁あって、机を林経においており、ゼミ、懇親会に出てもらっている。山梨県山梨市出身。専門は、近世〜近代の林政史・環境史。林業経済学会学生論文賞受賞。
博士課程以降:
SIRIVONGS Khamfeua
通称フアさん。ラオス出身。国立林業大学卒。オーストラリア国立大学大学院修士修了。保護地域管理とエコツーリズムに関する住民意識をラオスの国立自然保護区で明らかにする。日本で生まれた初めての娘さんを「ゆみこ」と命名。現在は、博士課程を終え(単位取得満期退学)、帰国後、『Forest Policy and Economics』誌に論文掲載に成功したが、課程博士の学位取得には間に合わず。現在、林業大臣秘書官。論文博士を目指すか?
安部 華枝
山形大農学部卒。農工大大学院国際環境農学専攻で修士課程修了。博士課程2年生から林経に移って来た。旦那さんの赴任で滞在したタジキスタンをフィールドに、首都における街路樹を中心とした都市緑地の管理問題に取り組んでいる。2012年度で博士課程を満期退学後、造園学会誌に投稿論文が受理され、旦那さんの次の赴任地ケニアで、課程博士学位取得に向けて学位論文執筆中。
MUDACA, Joao Daniel
通称ジョジョさん。モザンビーク出身。母国の国立大学EDUARDO MONDLANE 大学農学部農業工学科を卒業後、NGO勤務を経て、本学大学院国際環境農学専攻で修士。博士課程から林経に。温暖化対策を目的とした先進国からの資金提供による森林保全事業(いわゆるPES)が住民生活に及ぼす影響について、モザンビークとフィリピンの事例を比較研究。農村開発コンサルタント(NTCインターナショナル)に就職のため、2012年度、単位取得満期退学。学位取得目指して、論文投稿中。
大学院
博士課程:
加藤 恵里 D3
農工大地シス学科卒・大学院農学府自然環境保全学専攻修了。横浜市出身。野生動物と人間との関係を、獣害の深刻な地域における住民の動物及び被害に対する認識を中心に捉えようとしている。栃木県佐野市の3地区における住民の被害認識の比較調査で修士論文をまとめ、その成果を国際研究集会等で発信。半年間の一般財団法人自然環境研究センター嘱託職員を経て、昨年7月から大分大学経済学部特任助教。大分の中山間地域における、学生による地域支援プロジェクトを切り盛りしつつ、社会人学生として学位取得を目指す。
GHULAM, Hussain Poya D1
ポヤさん。アフガニスタン出身。カブール大学農学部森林・自然資源学科を卒業後、母校に助手として勤務し、数々の講義を担当。協定校である農工大で博士号を取るべく文科省国費留学生として来日。研究テーマは、母国中央部バーミヤン州での集落を基盤とした自然資源管理を、国立公園管理、流域管理を対象に把握すること。修士論文では、母国の初の国立公園である Band-e-Amir National Park における住民参加型の意志決定組織の機能および周辺住民の公園管理に対する認識をまとめ、2014年11月仙台で開かれたAsia Park Congressで発表した。2012年9月に家族を呼び寄せ、長女は小平市内の小学校に通う。
平原 俊 D1
農工大地シス学科卒・2012年度大学院農学府自然環境保全学専攻修了。東京都調布市出身。13年度から、東京都庁に造園職で就職。港湾局に配属され、一年間、海浜公園の現場事務所で修行の後、本庁に呼び戻される。それを機会に、社会人学生として連合農学研究科進学。修士論文では、鎌倉市広町緑地を舞台とした市民の開発反対運動、緑地保全活動の過程を、詳細な聞き取り調査により分析した。卒論は、群馬県旧六合村の重伝建指定過程における合意形成。
木山 加奈子 D1
東京都町田市出身。高校の時、森林総研多摩森林科学園が主催する環境教育プログラムに参加して、この分野に興味を持ち、農工大地シスに入学する。そして、初心貫徹して広い意味での環境教育で卒論、修論を書いた。卒論のテーマは、森林・林業学習施設(展示施設と森林)の管理の実態とその森林環境教育活動の場としての役割評価。修士では、各施設での地域住民を中心としたボランティア団体の役割に絞った。博物館学芸員公募に挑戦し続け、ついに「埼玉県立自然の博物館」の正規学芸員に。ひとまず博物館員としての修行のため、休学中。
修士課程:
宮崎 亮一 M2
兵庫県姫路市出身。農工大地シス学科卒。所属は大学院国際環境農学専攻。土屋は副指導教員だが、訳あって、今年度から林経所属に。大鹿村での「地域生態システム学実習 I 」の第一期生。卒業論文は環境倫理学研究室で書き、修士もMI所属で、常に土屋との関係は保ちつつ、ある距離以下に近づくのを避けてきたが、7年目に軍門に下る。ラオスのビエンチャン近郊農村における、住民による小規模木炭生産の実態分析が研究テーマ。現在、療養のため休学中。
新山 佳菜子 M2
東京都杉並区出身。農工大地シス学科卒。卒論では、都市近郊地域における保護地域のあり方を、東京都が条例に基づいて指定・管理している自然環境保全地域について、企業・NPO・住民の視点から広く分析した。昨年度は、ゼミ係として研究室運営を仕切る。現在の研究テーマは、国定公園における協働型管理の実態と課題。国「立」ではなく、国「定」にこだわっている。林経女子の内、歴代多い「武道系女子」の1人(合気道)。
成瀬 むつみ M2
愛知県安城市出身。 農工大地シス学科卒。 卒論は、行政と住民の協働による緑地保全の仕組みとしてのナショナルトラストに注目し、都道府県が主導するナショナルトラスト団体の機能の解明を、神奈川、埼玉、大阪の団体を事例にまとめた。修士課程では、一転して、最近、設立の増えている「地域住民自治組織」と公民館の連携のあり方について、飯田市を事例に探ることに。就職では、国や県ではなく、住民に近い市役所勤務を希望して、生まれ故郷も含めて挑戦中。
宮子 雄将 M2
埼玉県さいたま市出身。岩手大学農学部共生環境課程卒。林経3人目の岩大出身者。卒論は、指定管理者制度の運営の評価を、山梨県内の自然観察施設を事例にまとめた。修士課程では、文化的景観の保全に焦点を当て、重要文化的景観地域に指定された熊本県山都町などを調査地に合意形成過程の分析を予定。オタク的博識では林経で右に出る者がいない。読売東京ジャイアンツの熱狂的ファンなので、近くで巨人の悪口は言わない方がよい。
馬場 淳輝 M1
大分県別府市出身。農工大地シス学科卒。国立公園管理に強い関心を持ち、2012年春から半年間、米国カリフォルニア州・アリゾナ州で国立公園管理ボランティアの武者修行。さらに、10月からは、イギリスに渡り、シェフィールド・サーラム大学で聴講生として勉強しながら、伝統のピーク・ディストリクト国立公園の管理の聞き取り調査を実施。卒論としては、自然公園内の歩道管理に興味を持ったことから、北海道のロングトレイル「北根室ランチウェイ」の設立・展開過程を聞き取りによって明らかにした。修士課程では、国立公園における協働型管理の可能性という大きなテーマに挑戦する模様。
嶺 隆太郎 M1
神奈川県座間市出身。農工大地シス学科卒。今や林経では数少ない森林科学プログラム(林科)修了生。学部時は、森林資源管理学研究室(渡辺先生(演習林))に所属し、「ヤマツツジの菌根菌相」について演習林で調査研究して卒論をまとめた。この研究は楽しんだのだが、自然科学とは異なる社会科学から森林・林業を見てみたいと思い立ち、修士課程から林経に。テーマは、森林組合による施業集約化事業が森林所有者に与える影響。
学部
伊藤 寛隆 4年
土屋研。東京都葛飾区出身。当初から観光と地域の関係について研究したいという方向性はぶれていない。卒論テーマは、いまのところ、「観光まちづくりにおける持続可能な観光について」。大手旅行会社との関係について、地域の独自性を優先した黒川温泉(熊本県)に興味を持っている。旅行会社内定。
大慈彌 亮太 4年
加用先生初弟子の一人。大分県大分市出身。地シスでは少数派のインドア派。ただし、高校時代はテニス部に燃えた。林経二人目の大分県出身で、大分を深く愛す。卒論テーマは、木質バイオマスのLCA( Life Cycle Assessment)。就職内定。
佐藤 翼 4年
加用先生初弟子のもう一人。 宮城県仙台市出身。震災時、後期試験を受験すべく、たいへん苦労して農工大にたどり着いたら、農工大職員に冷たく中止を告げられ、途方に暮れたが、故郷に帰ることもできず、1週間東京を転々としたという経験を持つ。海外旅行経験豊富。卒論テーマは、世界各国の木材需要の時系列的変化の分析。商社志望だが、その前の修行として大学院を目指す。
苗代 夏菜 4年
土屋研。東京都練馬区出身。得意技はアイソレーション(気持ち悪い動き)だそうです。林経での行動も、けっこうアイソレーションしてます。海外の世界遺産を訪れるのが趣味。卒論テーマは、世界遺産から繋がって、自然観光地域における 他地域出身エコツアー業者の位置づけと役割。緑化会社内定。
三井 貴也 4年
土屋研。山梨県甲府市出身。しかし、テレビを持っていないので、NHK朝ドラ「花子とアン」で甲府が有名になっていることを知らなかった。ワンダーフォーゲル部に所属し、頻繁に山行している。その繋がりで、卒論テーマは、自然公園におけるローカル・ルール策定過程における合意形成。大学院志望。
最終更新日:2014年6月29日

2011年度合宿ゼミ(東京都奥多摩町・鳩ノ巣)



2009年度合宿ゼミ
(静岡県伊東市)
2010年度合宿ゼミ(神奈川県湯河原町)
2008年度合宿ゼミ
(東京都奥多摩町)

2012年度合宿ゼミ
(山梨県山中湖村)


2013年度合宿ゼミ(千葉県富津市)